
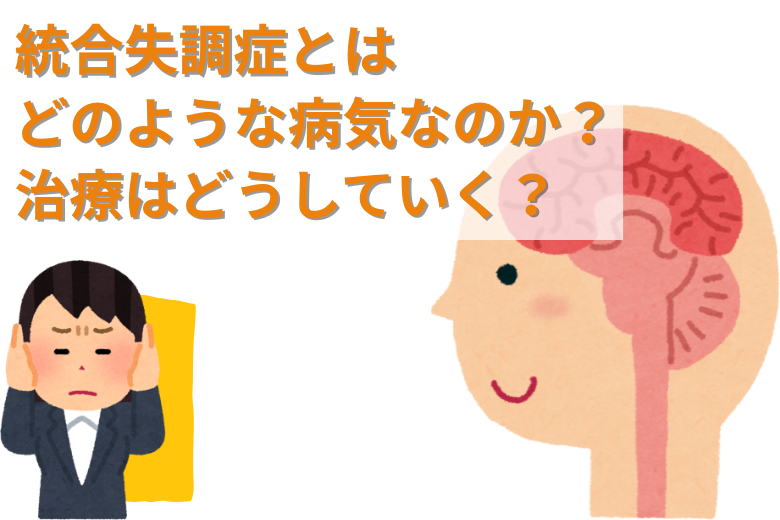
統合失調症という言葉を聞いたことはあっても、その実際の姿を具体的に
思い描ける人は少ないかもしれません。
「怖い病気」という漠然とした印象を持つ方もいれば、
「幻覚や妄想が出る病気」
という断片的な知識をお持ちの方もいるでしょう。
しかし、統合失調症は決して理解不可能な病気ではありません。
近年の研究によって、その背景には
「脳内の神経伝達物質のバランスの乱れ」
が関わっていると考えられています。
その代表的な説明が「ドーパミン仮説」です。
この記事では、ドーパミン仮説を手がかりに
統合失調症の特徴をわかりやすく解説し、
さらに治療の考え方や回復への道筋についてご紹介します。

私たちの脳の中では、無数の神経細胞が「神経伝達物質」
を使って情報をやりとりしています。その一つが ドーパミン です。
ドーパミンは、快楽ややる気をもたらし、人間が意欲的に生活する上で
重要な役割を果たしています。
しかし、脳のある領域でドーパミンが過剰に分泌されると、
感覚や思考が過敏になりすぎることがあります。
普段なら気にならないような音や光が強調され、
世界が「必要以上に鮮やかで騒がしい」ものに感じられてしまうのです。
これを研究者たちは「覚醒状態」と呼んでいます。
覚醒状態にあると、次のような体験が起こり得ます。
初期には「キーン」「ブーン」といった単純な音に過ぎませんが、
進行すると「自分を批判する声」として聞こえるようになることもあります。
これは「幻聴」と呼ばれます。
また、後頭部の視覚野が過敏になれば、実際には存在しない像が
見えたり、周囲の風景が不自然に変化して見えることもあり、これを「幻覚」といいます。
感覚の過敏さは、やがて「考え方」にも影響します。
他人の行動を先回りして解釈し、「悪意があるのでは」
「自分を害しようとしているのでは」と疑いが強まります。
これが「被害妄想」と呼ばれる状態です。
また、思考が過剰に加速し、次々に考えが浮かぶものの整理が
追いつかず、会話や行動がまとまりにくくなることもあります。
本人にとっては筋道立てて話しているつもりでも、
周囲からは混乱して見えてしまうのです。
統合失調症に特徴的な症状として「自我障害」があります。
例えば歯磨きをしているとき、「歯を磨いているのは自分だ」
と頭では理解していても、感覚としては「自分がやっている気がしない」
と訴えるケースがあります。
これは「行動と主体感覚のズレ」であり、他の精神疾患では
あまり見られない独特の体験です。

うつ病や不安障害の治療では「薬」と「心理療法(カウンセリングなど)」
を組み合わせることが多いですが、統合失調症においては 薬物療法が中心 です。
ドーパミンの過剰分泌は、本人の努力や環境調整だけで
抑えることは難しく、薬で脳内の働きを調整する必要があります。
もちろん軽症例では心理的支援も効果的ですが、医療機関を受診する
レベルの症状では薬物療法が不可欠です。
1950年代以降、統合失調症には「抗精神病薬」と呼ばれる薬が使われてきました。
古くからある薬(第一世代)は、確かな効果を
持つ一方で、副作用も目立ちました。
例えば、手の震え、筋肉のこわばり、よだれ、話しにくさなどです。
さらに重度になると
「体が硬直する」
「口の周りが勝手に動く」
といった症状も起こり得ました。
こうした課題を解決するために開発されたのが「第二世代の抗精神病薬」です。
20年ほど前から使われ始め、現在では リスペリドン(リスパダール)
をはじめ、オランザピン、クエチアピン、ルラシドン、ペロスピロンなど、
多くの新薬が登場しています。
これらの薬は副作用をできる限り抑えながら、十分な効果を
発揮することを目指しています。
患者さんの生活スタイルや体質に合わせて選択肢を
広げられるようになったのは大きな進歩です。

統合失調症の治療で最大の課題は「服薬の継続」です。
こうした理由で中断する人は少なくありません。
そのため医師は「なぜ飲み続ける必要があるのか」を患者さんと共有し、
納得感を持って治療を進めることを大切にしています。

「幻覚や妄想がある」と聞くと恐ろしく感じるかもしれません。
ですが、薬物療法をしっかり続けることで多くの方が症状を抑え、社会生活に復帰しています。
実際、治療を受けながら仕事を続けている人や、家庭を築いている人も数多くいます。
早期の診断と治療がその後の生活に大きな違いをもたらすのです。
統合失調症は「理解すれば対応できる病気」です。
正しい知識を持ち、偏見をなくすことが、患者さんと
周囲の人々にとって大きな支えになります。