
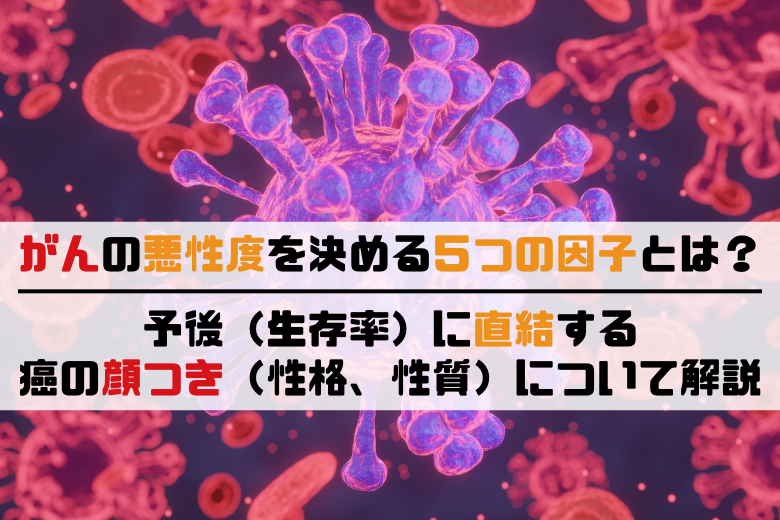
がんと聞くと、多くの人が「怖い病気」というイメージを持つと思います。しかし、実は一口に「がん」といっても、その性質やふるまいは大きく異なります。ゆっくり進行してほとんど命に関わらないものもあれば、短期間で急激に悪化してしまうものもあります。
この “がんがどのようにふるまうか” を表すのが「悪性度」です。悪性度とは簡単にいうと、
といった がんの性格の強さ を示すものです。
たとえば、悪性度が低いがんでは、検査で見つかったとしても、「しばらく様子をみましょう」と経過観察が選択されることがあります。一方、悪性度が高いがんでは、診断を受けてから短期間で病状が進行してしまうことがあり、どれほど治療を行っても完治が難しいこともあります。
つまり、 がんの悪性度はそのまま“予後(生存率や治りやすさ)”に直結する重要な指標 なのです。
では、この悪性度は何によって決まるのでしょうか?
実は、がんの悪性度を左右する要素はさまざまですが、ここではとくに重要な 5つの因子 を、できるだけわかりやすく解説します。
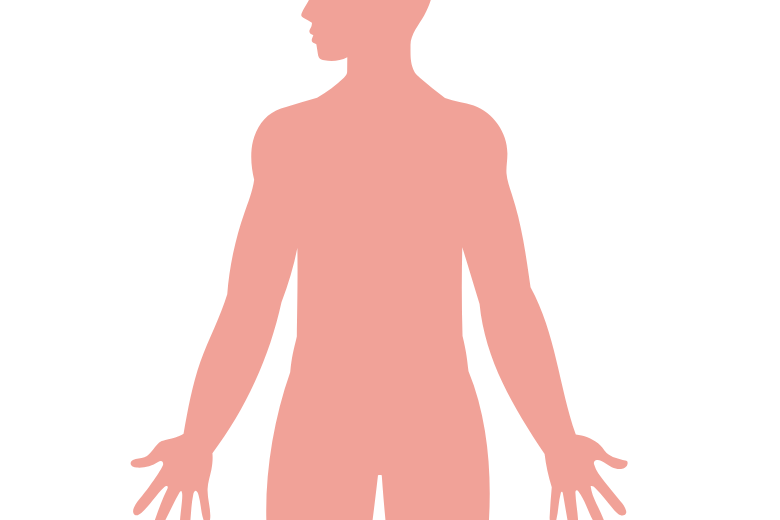
がんは体中のあらゆる場所に発生します。その発生した部位によって、がんのふるまいや治療のしやすさは大きく異なります。
たとえば、
といったように、同じ「がん」という名前でも発生場所によって予後は大きく変わります。
なぜ部位によって悪性度が変わるのでしょうか。
その理由は、
各臓器の構造や役割、血流、リンパの流れ、周囲の細胞との関係、症状が出やすいかどうか といった要因が複雑に絡みあっているためです。
たとえば、すい臓は体の奥深い場所にあり、がんができても自覚症状が出にくいため、見つかった時には進んでいるケースが少なくありません。これが「すい臓がんは悪性度が高い」と言われる背景のひとつです。
同じ臓器のがんでも、「どの細胞ががん化したのか」によって予後が大きく変わります。医師が「組織型(そしきがた)」と呼ぶものです。
典型的なのは肺がんの例です。
肺がんとひとことで言っても、
など、複数のタイプがあります。
このうち 小細胞がん は非常に増殖が速く、転移もしやすいため、「肺がんの中でも特に悪性度が高い」と言われます。一方で、腺がんは比較的ゆっくり進行するタイプが多いとされています。
このように、
“どの細胞からがんが始まったのか”という違いが、がんの攻撃性を左右する のです。
「分化」とは、がん細胞がどの程度“元の正常な細胞らしさ”を残しているかを示す概念です。
一般的に、
分化度が低いほど悪性度が高い とされています。
なぜかというと、正常の細胞に近い高分化のがんは増殖が遅く、比較的おとなしい性格であることが多いのに対し、低分化のがんでは細胞の増殖や転移のスピードが速く、治療に抵抗しやすい傾向があるためです。
医師が病理検査の結果を見て「低分化型です」と言う場合、それは治療方針や予後を考えるうえで非常に重要な情報になります。
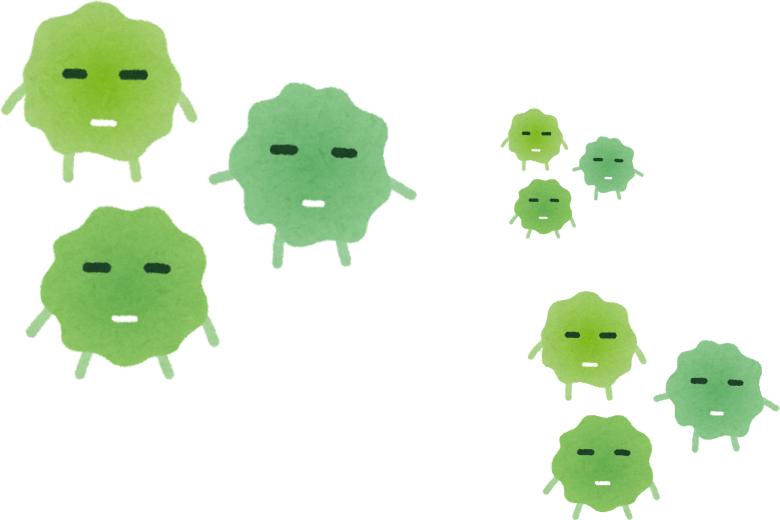
がん細胞がどれくらいのスピードで増えるかという点も、悪性度の重要な指標です。
増殖スピードが遅いがんは、たとえ大きさがある程度あったとしても、急激に悪化することは少ないため、治療の選択肢も広がります。逆に、増殖スピードが速いがんでは、短期間でがんが大きくなり、周囲の臓器に広がったり、遠くの臓器に転移したりしてしまう恐れがあります。
病理検査では「Ki-67(ケイアイ・シックスティーセブン)」という増殖マーカーを使って増殖能を評価することが一般的で、これは乳がんやリンパ腫などの診断でも重要な指標になっています。
がんは、正常な細胞の遺伝子に変化(変異)が起きることで発生しますが、この遺伝子変異の内容によって悪性度は大きく変わります。
近年のがん医療では、遺伝子解析によって
「どの遺伝子にどのような変異があるのか」
を詳細に調べることが一般的になりつつあります。
たとえば、
など、遺伝子変異はがんの性質を決める“設計図”のような役割を果たします。
また、1つだけでなく複数の遺伝子異常を持つがんは、より攻撃的な性質をもつことが多いとされています。

がんと言うと、「見つかったらすぐに治療しなければいけない」と思われがちですが、実際には 悪性度が低ければ急いで治療する必要がないケースも多い です。反対に、悪性度が高いがんの場合は早期に治療を始めなければ命にかかわることがあります。
つまり、
悪性度を正しく理解することは、適切な治療方針を選ぶための第一歩 なのです。
医学は日々進歩しており、以前は治療が難しいとされたがんでも、遺伝子解析の進歩や新しい抗がん剤の登場により、治療成績が向上している例も多くあります。
「がんの悪性度が気になる」「自分のがんのタイプを知りたい」という方は、遠慮せず主治医に質問してください。がんの“顔つき”を理解することは、大切な治療の基盤となります。