

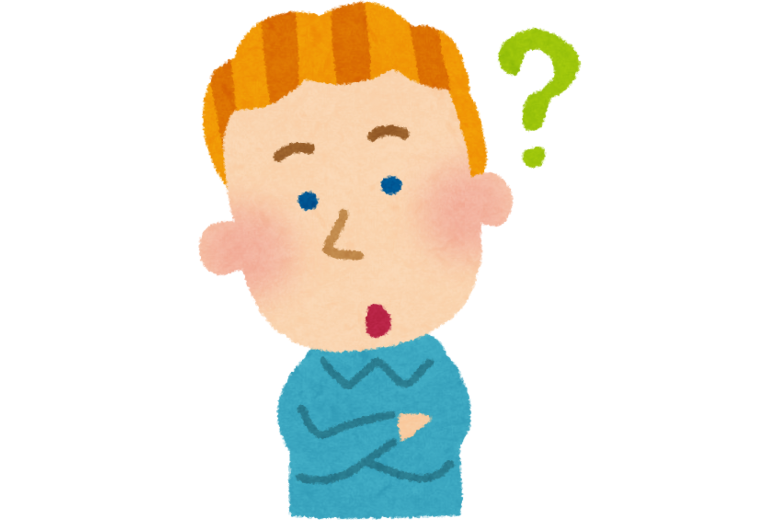
今回は、消化管に発生する腫瘍の一つである「GIST(ジスト)」について、その特徴と治療法をわかりやすく解説します。GISTという名前を耳にしたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、一般的な胃がんや大腸がんとは発生する場所や性質が大きく異なる腫瘍であり、近年注目されている疾患の一つです。

GISTは「Gastrointestinal Stromal Tumor」の略で、日本語では「消化管間質腫瘍」と呼ばれています。消化管の壁は内側から粘膜、粘膜下層、筋層などの層構造を持っていますが、GISTはそのうち「筋層」と呼ばれる部分に存在する間質細胞から発生する腫瘍です。そのため、粘膜から発生する一般的ながんとは成り立ちが異なり、性質や治療法も独自の特徴を持っています。年齢としては50〜60歳代に多く、発生頻度は人口10万人あたり1〜2人と比較的稀な病気とされています。
発生部位は胃が最も多く、全体の約70%を占めます。次いで小腸が約20%、大腸と食道がそれぞれ約5%と続きます。胃に発生するケースが多い理由は完全には解明されていませんが、臨床の現場では胃で発生するものが最も多く見られます。
GISTは、初期にはほとんど自覚症状がないため、発見されにくい傾向があります。粘膜の下にできる腫瘍であるため、内腔に大きく突出してこない限り症状が現れにくく、腫瘍がある程度大きくなって初めて異常を自覚する方も少なくありません。代表的な症状としては、腫瘍からの出血による吐血や下血、お腹の鈍い痛みや違和感、腹部のしこりを触れるなどが挙げられます。出血が持続することで貧血を起こし、検査によって見つかるケースもあります。
一方で、実際には症状とは無関係に、がん検診や別の疾患の精査のために受けたX線造影検査、内視鏡検査、CT・MRIなどで偶然見つかることが多くなっています。医療機器の発達によって、無症状のうちに発見される例が増えているのは大きな進歩といえるでしょう。
診断には、消化器造影検査、内視鏡検査、CT・MRIなどが用いられますが、最終的な確定診断には病理検査が必要です。特徴的なのは、GISTの多くが「c-kit(シーキット)遺伝子」の突然変異を持ち、それによってKIT蛋白が異常に発現している点です。組織を採取し、免疫組織染色という特殊な検査でKIT蛋白を確認することで診断が確定します。

治療選択は腫瘍の大きさや進行度によって異なります。2cm未満の非常に小さな腫瘍の場合は、すぐに治療を行わず、定期的に画像検査を行いながら経過を観察することがあります。一方で、2cm以上の腫瘍に対しては手術が検討されます。手術可能なGISTに対しては外科的切除が第一選択となり、腫瘍を完全に切除できれば予後は比較的良好であることがわかっています。完全切除例の5年生存率は50%以上とも報告されており、早期発見と適切な治療が非常に重要です。
手術方法には、お腹を大きく開く開腹手術と、小さな穴からカメラと器具を挿入して行う腹腔鏡手術があります。腫瘍の位置や大きさによって適切な術式が選択されますが、近年は腫瘍が比較的小さい場合には腹腔鏡手術が選ばれることも増えています。ただし、腫瘍の位置によっては腹腔鏡では技術的に難しいこともあります。
切除が難しい場合や再発した場合、または完全に切除できなかった場合には、分子標的薬と呼ばれる薬物治療が用いられます。最もよく使用されるのが「イマチニブ(グリベック)」で、c-kit遺伝子の異常によって活性化されたKIT蛋白の働きを抑えることで腫瘍の増殖を抑制します。イマチニブが効かない場合には「スニチニブ(スーテント)」、さらに耐性が生じた場合には「レゴラフェニブ(スチバーガ)」といった薬が使われ、治療の選択肢は近年大きく広がっています。このように、GISTは分子標的薬の登場によって治療成績が大きく改善した代表的な腫瘍といえます。
再発は手術後3年以内に起こりやすいとされていますが、10年間は長期的な経過観察が必要といわれています。再発部位としては、腹腔内の局所再発や腹膜への播種、肝臓への転移などがよく見られます。
今回の記事では、GISTの特徴、症状、診断方法、治療までを総合的に解説しました。GISTは稀な腫瘍ではありますが、早期に見つかれば治療の選択肢も広く、良好な予後が期待できる病気です。正しい知識を持ち、適切な検査や治療につなげることが大切です。