
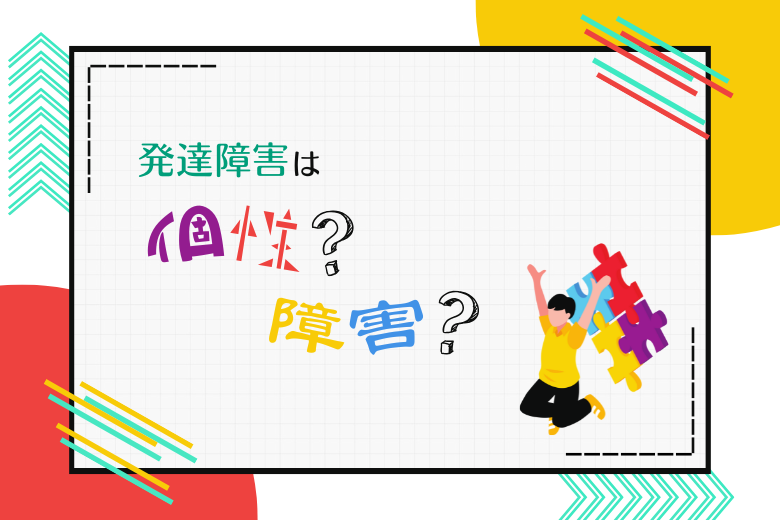
発達障害は「個性」なのか、それとも「障害」なのか。この問いは、長年にわたり医療や教育現場、さらには発達障害の当事者やその家族の間で議論されてきました。発達障害の特性は人それぞれ異なり、その影響の受け方も一律ではありません。
結論から言えば、発達障害は「障害であり、個性でもある」と言えます。しかし、その捉え方は人によって異なり、特に社会的なサポートの有無や環境によっても変わります。本記事では、発達障害の特徴を整理し、その捉え方の変遷、社会における考え方の違いについて詳しく解説していきます。

発達障害とは、生まれつき脳の機能に偏りがあることによって、日常生活や社会活動において困難が生じる状態を指します。その代表的なものとして ADHD(注意欠如・多動症) と ASD(自閉症スペクトラム障害) があります。
ADHDは、「不注意」「多動性」「衝動性」が主な特徴です。
これらの特性により、学業や仕事でミスが増えたり、人間関係で誤解を生むことがあります。
ASDは、主に「対人コミュニケーションの困難さ」「興味や行動のこだわり」が特徴です。
ASDの人は、コミュニケーションのズレから誤解されることが多く、社会生活の中で生きづらさを感じることがあります。
発達障害は、幼少期に発見されることが多いですが、近年は成人になってから診断を受けるケースも増えています。医学的には「完治するもの」ではなく、生涯にわたってその特性と向き合っていく必要があります。また、社会的なストレスによって二次障害(うつや不安障害など)が生じることもあり、適切なサポートが重要です。
発達障害の捉え方について、日本や海外では様々な議論がなされてきました。以下に、その変遷を整理します。
かつて日本では、発達障害は「治らない障害」として認識されていました。診断を受けた当事者は、「一生このままなのか」と絶望感を抱くことも多かったのです。このため、「診断を受ける意味があるのか」「むしろ自信を失うだけではないか」といった批判も生まれました。
しかし、近年では「発達障害は個性の一つ」という考え方が広がり、特性を活かす方法が模索されるようになっています。例えば、ADHDの人が持つ創造性や行動力、ASDの人が持つ専門性の高さや集中力の強さは、適切な環境では大きな強みとなることもあります。
ただし、「個性」として認識されることで、新たな問題も生じています。例えば、「個性ならば努力で改善すべきだ」とのプレッシャーが当事者にかかるケースも増えてきました。「発達障害は個性だから頑張ればできるはず」と言われることで、障害による困難が軽視される場面もあります。
アメリカでは、1990年代以降「ニューロダイバーシティ(神経多様性)」の概念が広まりました。これは、「発達障害を欠陥ではなく、多様な脳のあり方の一つとして認める」という考え方です。
この考え方が普及したことで、発達障害を持つ人々が「自分たちは障害者ではなく、社会の中で適応する方法を模索すべき存在」として捉えられるようになりました。最近のアメリカのドラマや映画では、発達障害のあるキャラクターが「ユニークな才能を持つ人物」として描かれることが増えています。
一方で、「障害としての側面を無視するのは問題だ」という指摘もあります。特に、支援を受けるためには「障害」としての認識が必要であり、個性論だけでは救われない人々もいるのが現実です。
発達障害を「障害」として受け入れるのか、「個性」として受け入れるのかは、一人ひとりの状況によって異なります。一般的には、以下のような段階を経て、自分なりの受け入れ方を見つけていくことが多いです。

発達障害は、一面的に「障害」または「個性」として捉えるものではありません。
重要なのは、一人ひとりに合った捉え方を尊重し、適切なサポートを受けながら生きやすい環境を整えていくことです。社会全体が発達障害について理解を深め、個々の特性に応じた柔軟な対応が求められています。