
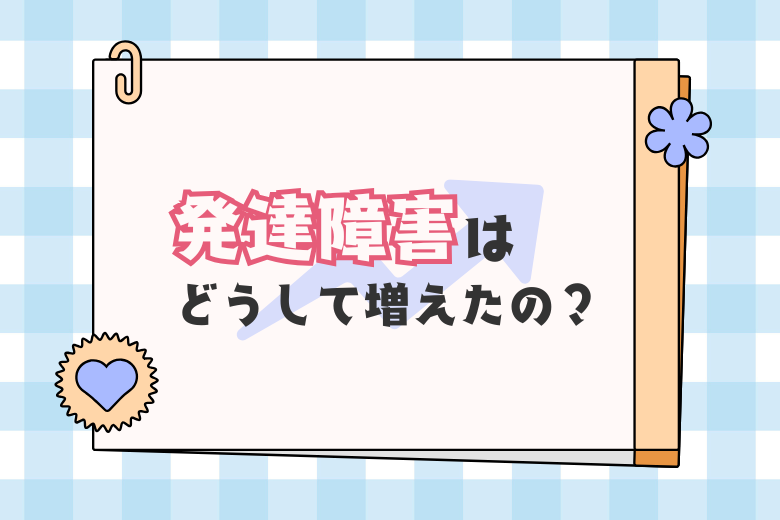
「発達障害はなぜ増えているのか?」という問いに対しては、実際に障害そのものが増加しているというよりも、「診断される人が増えた」というのが実情に近いと考えられます。
実際、文部科学省の調査では、小中学生の約8.8%に発達障害の可能性があるとされています。また、成人や女性への診断も以前より増加傾向にあります。こうした変化の中で、子どもが診断を受けたことに戸惑う保護者や、成人してから診断を受けて「もっと早く分かっていれば」と悔やむ人からの相談も少なくありません。
発達障害が話題になることが増える中で、インターネット上には偏見を助長するような情報も見られます。一方で、自ら発達障害を名乗る人が増えたことも、新たな問題として取り上げられるようになりました。
では、なぜ「診断される発達障害」が増えたのか。その主な理由として、以下の4つの要因が挙げられます。
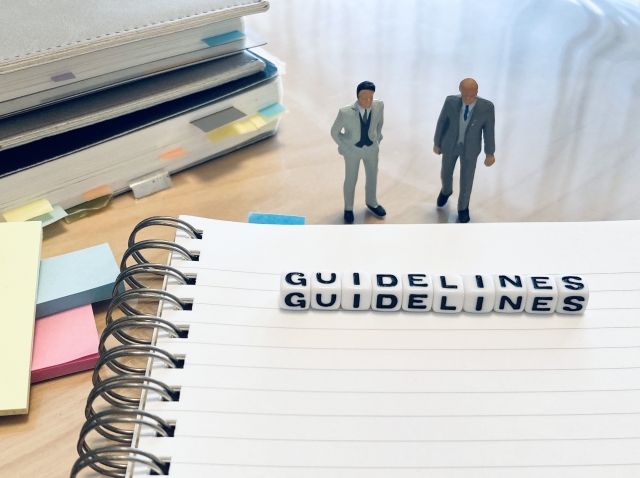
まず注目すべきは、診断基準自体が変わったという点です。
かつては明らかな社会的トラブルや強い孤立が見られる場合にのみ診断される傾向がありました。たとえば、ASD(自閉スペクトラム症)であれば対人関係での深刻な問題が前提とされていたり、ADHD(注意欠陥・多動性障害)であれば衝動性が原因で軽犯罪などに至るようなケースが診断の対象でした。
しかし、アメリカのDSM-5(精神障害の診断と統計マニュアル 第5版)の導入により、診断の枠組みが広がりました。ASDは以前のように細分化されず一つのスペクトラムとして統合され、より軽度な特性を持つ人も診断の対象になりました。ADHDにおいても同様に、診断基準がやや緩和されたことで、広い範囲の人が対象となっています。
次に挙げられるのが、発達障害に対する認知度の向上です。
かつては限られた専門家や関係者しか詳しく知らなかった発達障害について、現在ではネットやメディアを通じて多くの人が情報を得られるようになりました。自分自身で調べて「もしかして自分も?」と相談に来る人が増えています。
教育現場でもその理解は進み、保育士や教師が早い段階で子どもの特性に気づくことができるようになりました。有名人によるカミングアウトも、発達障害への理解を促すきっかけになっています。特にADHDのように、「克服可能な個性」としてポジティブに受け取られる風潮も見られます。
ただし、認知の拡大とともに、「自称発達障害」の問題や、それに対する社会の偏見が浮き彫りになっている点も無視できません。
発達障害が早期に発見されることが増えた背景には、「未診断による二次障害の防止」が強く意識されるようになったことがあります。
たとえば、診断を受けないまま生きづらさを抱え続けると、うつ病や不安障害などの二次障害を併発するリスクが高まります。こうした事態を未然に防ぐため、子どもでも大人でも早期発見・早期介入が推奨されるようになってきました。
現在では、放課後等デイサービスなどの小児向けの支援に加え、成人向けには就労移行支援などの社会復帰を目指すサポートも少しずつ整いつつあります。情報も以前より充実し、個人の工夫や対応策にアクセスしやすくなったことで、診断を受けるハードルも下がっています。

現代社会の変化もまた、発達障害の特性を「浮き彫り」にする要因となっています。
仕事における効率重視、マルチタスク、時間厳守といった要求水準の上昇は、発達障害の特性を持つ人にとって強いプレッシャーとなります。特に日本では、経済的な余裕や「見逃してもらえる環境」が少なくなったことが、特性の顕在化を招いているともいわれています。
ADHDの方にとっては、厳密な時間管理や感情調整が求められる場面が多くなり、結果としてトラブルや誤解を招きやすくなりました。ASDの場合も、変化への対応や曖昧な人間関係、雑談などのコミュニケーションの比重が高まることで適応困難を感じることが多くなっています。
さらに、AIなどの進化により「知識を蓄えておけば安心」という時代が終わりを迎え、個性や柔軟な対人能力が重視されるようになったことも、発達障害を持つ人にとっての障壁となりつつあります。
このように、発達障害の「増加」とされる背景には、診断基準の拡大、認知度の上昇、支援体制の整備、そして社会の変化が複合的に絡んでいます。
つまり、発達障害そのものが増えているというよりも、「見つけられるようになった」「診断されやすくなった」ことが主な理由といえるでしょう。これは、これまで苦しんでいた人たちが適切な支援を受けやすくなるという意味でも、必ずしも悪いことではありません。
重要なのは、社会全体がこうした背景を理解し、それぞれの特性を受け入れる柔軟な目を持つこと。そして、発達障害という「個性」とどう付き合っていくか、支え合っていくかという視点が、これからの社会に求められているのです。